「ここ…?」
不安そうに問う窓花に、エレンは元気よく頷いた。元気がよいのはいいが、キョロキョロと辺りを見渡しているのを見ると、少しばかり頼りない。
「あれ? いないのかな……」
ポツリと独り言を呟き、エレンは窓花の手を握ったまま歩き出した。たくさんの機材の間をすり抜け、何度もエレンは上を見上げる。時折シルクハットを持ち上げて倉庫内を見回した。
「あっれ〜?」
倉庫に入ってから何度目かの呟き。エレンは困ったように首を傾げ、窓花と機材を交互に見た。
「どうしよ……えっと、うーんっと……名前叫んだら出てきてくれるかな?」
「おなまえ…?」
「えっと、確か……あれ? 誰だっけ」
「…いらいのひと?」
「うん、そう。お電話で依頼されたの」
「てがみやさん、たいへん?」
「そうでもないよ? 楽しいっ!」
手紙屋。それが彼の職業だ。
彼の所属する手紙屋は、多種多様な『手紙』を運ぶ、謂わば運び屋のような組織だ。『手紙』は内容を問わず、小さな紙切れだって運ぶし、今回のように人間を運ぶ時もある。彼がソレを『手紙』だと判断すればよいのだ。
「今回は、あの路地裏にいる人をここに連れて来いって言われた。そしたらハナちゃんがいるんだもん。ビックリしちゃった」
ニヘラと笑ったエレンは、もう一度機材の上を見上げる。
その時。
「ご苦労だったな」
背後から突然降ってきた言葉と共に何か硬いもので頭部を強く殴られ、エレンの体が傾いだ。目深に被っていたシルクハットが外れ、赤黒い髪が薄暗い倉庫内に鮮やかな色彩を落とした。
「エレン…っ!?」
「ようこそ、移木のお姫様」
そう言って男は窓花の口元に薬品で湿らせた布を当てる。甘い匂いのそれが気管に入ると同時に急速に意識に靄がかかったようになり、ぐらりと小さな体が傾ぐ。
それをやや乱暴な仕草で受けとめ、男は暗い笑みを浮かべた。
窓花を抱きかかえたまま携帯電話を取り出し、どこかへと電話をかけ始める。数コール待った後、相手が電話に出た。
『……何の用だ』
電話相手――彼の上司は普段と変わらぬ感情の見えない声で応じる。
脳裏に己よりも少々年下の氷じみた美貌を思い浮かべ、意識せず姿勢を正してしまう。
「先日企画書を提出した通り、移木の当主を誘い出し、捕えました。少々想定外のこともありましたが、これから予定通り監禁し、《番犬》を始末して我が主へ献上しようと思います」
丁寧な報告に上司は先程と変わらない口調で言い放つ。
『情報の伝達が正確ではないようだな。貴様の企画は却下したはずだが?』
「しかし我が主。代替わりした現在の移木は我々にとって恐るるに足らない雑草のようなもの。《番犬》さえ消せば、いくら移木とはいえ壊滅させるのは容易いことです。それをなぜ放置するような真似をなさるのですか」
『貴様には理解できないのだろうな。だが俺は先日の会議で[しばらくの間、移木には手を出さない]と通達したはずだ。それに、貴様ごときでは移木の犬は倒せない。』
上司は一度言葉を区切り、今まで以上に冷えた声音で言い放つ。
その言葉に男は僅かにいきり立つ。
自分はこの上司のもとで幾つもの修羅場を潜り彼の敵を排除してきた。確かに《番犬》は彼らの属する組織では一種伝説じみた噂が後を絶たず、彼に手を出すことは死を意味するとまことしやかに囁かれているのだ。
そんな化け物が数年前から何故か情報組織でしかない、代替わりをしたばかりの移木の背後についた。
先代の移木は冷酷非道な商いをしていたせいで敵も多かったが、それを受け流すだけの情報力があった。そこから流れる情報で多くの組織や個人が自滅に追い込まれたという。
しかし今代の移木は総帥が幼いせいか以前ほどの権力はない。その移木に何故《番犬》がついたのかは誰も知らないだろう。
男は噂は噂でしかないと考えていた。火のないところに煙は立たず、確かに相当の強さを備えているのだろうが、所詮は人間。噂が独り歩きして伝説化してしまうのはよくある話だ。
どんな人間であろうと銃で狙撃されれば容易に死ぬだろう。男は何故上司が移木に手を出すのをためらうのかが分からなかった。
抗議をしようと口を開こうとした瞬間、上司の氷の声が耳を打った。
『俺の思い通りに動かない駒は必要ない。犬のことだ、貴様の愚行は既に知られているだろう。正直これ以上移木の心証を悪くするのも今後に差し支える。この瞬間から貴様は我々と一切の関係を断ち、一個人として犬に始末されて来い』
吐き出された言葉は事実上の解雇。止まった思考に止めを刺すように通話が切れ、乾いた電子音が耳元で響いた。
「主……」
通話の切れた携帯を握りしめたまま、男は呆然と呟く。
自分は組織の為を思って今回の誘拐に踏み切ったのだ。それなのに、なぜこのような仕打ちを受けねばならないのか。
男は考える。しかし幾ら考えても上司の考えは理解できず、また納得もいかない。
あの上司が《番犬》の噂を鵜呑みにしているとも考えられないが、とにかく自分があれを始末すれば彼もきっと自分を見直し、理解してくれるだろう。
暗い倉庫の中、男は薄く笑う。懐の拳銃を手触りで確認してから、移木の幼い総帥と小さな手紙屋を奥の小部屋へと移すため乱暴に抱き上げた。
手紙屋はこの場で始末しても構わないのだが、万が一の時に何かしら役立つ可能性もある。念の為縄で縛ってから、しばらく総帥と一緒に転がしておくことにした。
運ぶ途中、手紙屋の小柄な体躯から大きな鞄が滑り落ちた。拾って同じ部屋に放り込もうとしたが、考え直す。もしも武器が入っていたら面倒だ。憂いは払っておくに越したことはない。男は落ちた鞄をそのままに、総帥と手紙屋を倉庫奥の小部屋に放り込んで外からしっかりと錠を降ろした。
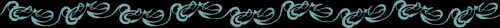
電話を切った青年は社長室の革張りのソファに背を押しつけた。
仕事に一区切りつけ、僅かな仮眠を取っていた矢先の、先程の電話。
常日頃から部下の教育は徹底してきたつもりだが、やはり甘かったのかと痛感する。
こんなことならば最初から力で捩じ伏せ躾けておけばよかった。拷問じみたそれに耐えうる者ならば、自分に有益な駒になるであろうことはわかっていたはずなのに。
「まだまだ甘い、か……」
自嘲気味に低く呟き、重厚な黒檀の机の引き出しから簡素な白い便箋と革紐を取り出した。
自戒ならばいつでもできるが、今はとりあえず、移木に対して何か手を打っておいた方が賢明だろう。
書き終えると便箋を丸めて革ひもで括る。
準備を終えると彼は一度短く強い指笛を吹いた。呼応するようにバサリ、と大きな羽音がし、首に細い鎖を幾重にも巻いた金の瞳の鴉が彼の肩に留まった。
「仕事だ。これを移木の屋敷に運べ」
囁くように命じると鴉は大人しく片足で丸められた便箋を掴む。
青年はカーテンの引かれた窓へ歩み寄り、鴉が出ていけるように大きく開け放つ。
「……行って来い」
言葉と同時に鴉が肩から飛び立つ。見送ることもなく窓を閉め、青年は再びソファへと腰かけた。
もう一度寝直そうとするが、数分もしないうちにドアの向こうから微かなノック音が聞こえる。新たな仕事を迎えるため、彼はソファに座り直し、静かな声でノックに応えた。
文章部屋へ