月が頭上高く上るころ、関所を超えて北の領土へ入ったところでマリアは立ち止まった。
「何がだ?」
「どうやってグレゴリオを誘い出すか、考えねばならぬだろう?」
マリアは顎に指を当て考え込む。ソウルイーターはこの国の貴族の事情に疎いので黙っているしかない。
「ふむ…やはり妾だけでは難しいかの。……汝、少し頼まれてはくれぬか?」
「……何をだ?」
何故かいやな予感がしながらもソウルイーターは応える。
「妾はまだフォーカロル家の次期当主でしかないが、グレゴリオの主フェヴェッツェ公は既にあちらの当主。妾ごとき小娘が
「それの何処に俺が介入するんだ」
「妾の言う問題はその後。妾は母上の見繕った者との見合いが嫌で家を出ておる。故に事が終わったら何とかして妾を家から連れ出してほしい」
「……金を回収するより難しそうだが?」
「だから汝に頼んでおるのだ。……駄目かや?」
ソウルイーターは困ったように頬を掻く。確かにマリアの話を聞く限り自分ひとりでは万屋の店主の頼みを叶えるのは難しい。
「何、事が終わった夜にでも連れ出してくれれば何とかなろう」
マリアが少々自信なさげに呟いた。ソウルイーターも連れ出す方法がそれくらいしか思いつかず、しかしとりあえず頷いた。
「ありがたい。ならばすぐに実行したほうがよいな。まずは妾の家へ向かうぞ」
「俺のことをどう言うつもりだ?」
「妾が旅の途中で拾ったボディーガードだとでも言っておく。名を名乗りさえしなければ問題はなかろう」
そう言ってマリアは彼らが出会った森の入り口へと向かった。夜の森は数メートル先すら見えないほどに暗く、あたかも二人の計画性の低い未来のようだった。
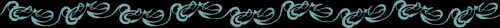
強い光でソウルイーターは目を覚ました。利かない視界で周囲を見回すと、どうやら室内のようだった。強い光はおそらく陽光だろう。
昨夜、日付が変わるころにようやくマリアの実家に着いた。セリカスタンから休むことなく歩き続けてきた二人を迎えたのはマリアの幼いころからの子守役だと言うメイドだった。ラナと名乗ったメイドはマリアが帰ってきたことを素直に喜び、彼女のボディーガードを名乗ったソウルイーターも快く受け入れた。
ラナの作った夜食を軽く食べてからソウルイーターは客間に通され、しばらく野宿続きだった彼はそのまま眠ってしまったのだ。
不意に、ドアのノック音が部屋に響いた。扉の外の気配を探るとマリアのようだったのでノックに応えて開いている、と声を上げる。
部屋に入ってきたマリアは久しぶりに入った客間に懐かしそうに目を細めてからソウルイーターに向き直り、朝食が出来た旨を伝えた。
「それとな、母上には汝の目が見えぬことは言ってあるが、それ以外汝自身のことは何も言っておらぬ。『魂喰らい』の噂はこの辺りでは有名な故、色々と聞かれてもあまり応えぬほうが得策だと思うのだがどうかや?」
「どう有名なのかは多少気になるところだが、どうせあまり良いものでもないんだろう。適当にかわす。グレゴリオのことは?」
「母上には昨夜の内に話だけはしておる。朝食の席で再度進言する予定なのだが……適当に話を合わせてくれぬか」
マリアの言葉に頷き、ソウルイーターは手早く部屋を出る支度を済ませた。
食堂には既にマリアの母、ミルカ=フォーカロルが席についていた。マリアに似た凛とした美貌はマリアほどの娘がいるとは思えないほど若々しい。
「そなたがマリアのボディーガードの者か。娘を守ってくれた事、深く感謝しよう」
女領主らしい威厳と母性に満ちた言葉にソウルイーターは無言で頭を垂れる。
「母上、昨夜も申したのですが……フェヴェッツェ公との面会、如何でしょうや?」
ラナから白米の盛られた茶碗を受け取りながらマリアは己とよく似た母を見つめる。
「気が早いの、マリアは。フェヴェッツェ公には昨夜のうちに妾が手配しておいた。今日の午後に迎えの馬車をやると仰っていたぞえ」
「感謝いたしまする、母上」
一度箸を置き目礼したマリアに満足げに頷き、ミルカはひどく楽しげに愛娘を見つめた。
「それにしても、こうも早く気が変わってくれるとは思わなんだ。やはり妾の目に狂いはなかったということか」
「まだ見合いではありませぬ、母上。如何ようなお方か知りたい、といったまでではありませぬか」
「どちらも同じじゃ。フェヴェッツェ公爵家といえば国王陛下より国境警備を任された軍務を司る家。商業を司る妾らフォーカロルと結べば必ずや善き方へ事が進むというもの」
上機嫌に白米を噛み締める母に反論することを諦めたマリアはソウルイーターが食べ終わったのを見計らって席を立つ。
「では母上、妾は午後の準備をします故これにて。汝、手伝ってたもれ」
マリアの呼びかけに頷き、ソウルイーターはミルカに一礼してから席を立った。
去っていく二人の背中を見つめ、ミルカは給仕をしていたラナに話しかける。
「ラナ、あのボディーガードとやらも見目麗しかったが、本当にただのボディーガードなのかや?」
「私にはわかりかねますわ、奥様。しかし一時期は男嫌いかとも思われた姫様にしてみれば、あの方とはとても息が合っているように思われます」
「妾もじゃ。あれで地位があれば、即座に婿に入れるのだがな」
ラナが淹れた緑茶をすすり、ミルカは残念そうにそう零した。
文章部屋へ