草木が揺れる。揺れた草木からぼんやりと黒い何かが見える。
「…数が多いな」
一つ呟き、形の良い眉を微かにしかめた。
周囲のエナジーから感じられるのは、生命のない冷たい無機質の気配。体温を持たない、無の気配。血の通った生物であれば、彼らの発するエナジーが自然と彼らの行動を教えてくれた。しかし己を取り囲むこの気配は、生物ですらない、俗に機械獣と呼ばれるものであった。
「(この状況は……)」
自分にとって、不利だ。
ソウルイーターはギリッと奥歯を噛み締めた。
彼は生命のエネルギーを吸いとることが出来る。しかし、それらは良い事ばかりではない。それは、エネルギーを吸い取るだけではなく、何故か獣を寄せ付けてしまう性質もあるのだ。おそらく、その性質がこの機械獣を呼び寄せたのであろう。
この機械達は、東の絶対国家セリカスタンによって造られた。その理由は、悪人を取り押さえるため。
しかし、ある時、突然制御できなくなったのだ。機械獣たちは暴走し、セリカスタンを逃亡して世界各国に散ったのだ。 セリカスタンは見つけ次第破壊するよう各国に呼びかけているが、高度な人工知能を持つ機械獣は山奥に潜むことが多く、まだ完全に回収できたとは言いがたいのが現状だ。
だがこの機械獣を破壊すること自体は容易で、繊細機器が集結している頭部を破壊すれば容易く壊すことが出来る。 ソウルイーターもそのことを知っていたが、彼は生まれつき魔法が使えない。また視力も極端に弱いため武術も得意ではない。
更に厄介なことに、エナジーを吸い取るという能力を使おうにもこの機械獣達は生きているわけではない。だから生命エネルギーが存在せず、吸い取ることも出来ないのだ。
「…逃げるか」
ソウルイーターは一人呟き、今まで以上に周囲に気を配る。己の周りを取り巻くエナジーの流れから、突破口を見つけ出そうとしたのだ。
けれど機械獣の数は多く、どうも逃げ切れそうにも無い。
どうしたものか、と思案していると、不意に自分以外の人間の気配を感じた。
ソウルイーターは機械獣に警戒しながらもそちらの気配に気を向けた。
気配の方には木が生い茂っていないようだ。森の出口に近いのだろう。ならば森から出ないこの獣達を撒いて外に逃げることも可能か。
ふと、外の人間の気配が変わった。こちらに気付いたのだろうか。
僅かな期待を胸に、ソウルイーターはそちらの気配に向かって一歩踏み出した。
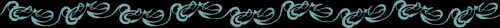
フェヴェッツェ公に送られた西の森から数分。
マリアはようやく関所に着いた。この関所はとても小さく、看守すらいない。しかし今のマリアにはそれが返って好都合だった。
扉の向こうから吹いてくる風は湿気を帯びて生温く、どことなく怪しい雰囲気に満ちた場所だった。
関所の壁や扉にはコケやらなにやらがびっしりと生えていた。しかし看守がいない代わりか、石造りの扉にはしっかりと錠がかかっている。扉を開く方法を訊こうにも、誰もいないので東へ出る方法も分からなかった。
ふと、自分以外の気配を感じ、マリアはわずかに身構える。母が自分を連れ戻すために放った使用人だろうか。それとも今の自分と同じように密かに北へ向かおうとする者か。
しかしその気配があるのは自分のいる道ではなく、関所に隣接する森の、木々の奥のほうからだった。
「何かや…?」
使用人だったら風で吹き飛ばせばいい。旅人ならばこの先へ行く方法を知っているかもしれない。マリアはひとり頷き、森の気配に向かって一歩踏み出した。
森へ入ったマリアが最初に見たものは、木々の陰に潜む複数の赤い光だった。光は全て己の膝丈ほどで、マリアにはそれが機械獣であることがわかった。
「かようなところに潜んでおったとは。妾も被害は避けたいところ、早々に破壊しようかの」
マリアは袖口からレースの扇を取り出し、思い切り横に薙いだ。機械獣たちは扇から生み出されたとは思えない風圧に吹き飛ばされ、あるものは生い茂る木々に叩きつけられ、またあるものは機械獣同士が衝突しあって破壊された。
「こんなものかや。……して、汝は誰ぞ?」
扇を畳んで木の影に声を掛けると、木立の合間から銀髪の青年が姿を現した。月の光のように白い肌と髪を闇色のマントのフードに隠した、自分より少々年上らしい青年。肩まで伸びた細い銀髪には、小さな金の鈴が揺れていた。
「お前は……何だ?」
静かな低い声で青年が問う。マリアは不機嫌そうに眉を顰めた。
「仮にも妾は汝を助けてやったのだぞ? まずは顔を見せ、礼を言うくらいのことはせぬか?」
貴族らしい高圧的な態度に青年は軽く息をつき、顔を覆っていたフードを外した。
「……助けてくれたことには礼を言う」
「うむ。して、汝の名は?」
「俺に名はない。周りは俺の事をソウルイーターと呼んでいるがな」
ソウルイーターの名にマリアは少しだけ眉を上げる。
噂では『魂喰らい』の異名を持つ流浪の魔術師と聞いていたが、先ほどから観察していても魔力は欠片も感じられない。噂は所詮噂というところか。
「して、ソウルイーター。何故かような所に?」
「………迷ったんだ」
最初は確かにセリカスタンに向かおうとしていた。しかしこの容姿と能力のため人目を避けるように歩いていたら、いつの間にか関所への道を見失ってしまったのだ。視力もほとんど無いため地図を見ることも適わず、この森の中で立ち往生しているところを機械獣に襲われた。
一連の事情説明の後、マリアは納得したように一人頷き、そしてふとソウルイーター胸元で光るものに目をつけた。
「それは何かや?」
「何がだ?」
「その胸に下げているものだ」
マリアが指差したのは、子供の拳ほどの大きさの緑色の宝珠。革紐が巻きつけられ、首に下げられるようになっているそれからは強い魔力が感じられる。
宝珠の芯はぼうっと弱い光を放っており、魔術の増幅装置の役割を担うことが見て取れた。
ソウルイーターはあぁ、と納得するとそれを首から外す。
「珍しいか?」
「魔術の増幅装置であろう。しかしこれほど大きく強力なものは初めて見た」
ソウルイーターから受け取った宝珠を観察するマリアを感じ、彼はしばし考えてから言った。
「ならばお前にやろう。魔力のない俺が持っていても仕方ないものだ」
その台詞にマリアはソウルイーターの顔をまじまじと見つめる。
そもそも増幅装置は司法機関であると同時に大陸唯一の魔道具生産国であるセリカスタンから輸出される、マリアたち貴族でもなかなか手が出せないほど高価な代物だ。それをこうもあっさりと貰うことにマリアは少し躊躇った。しかし確かに魔力のない者には邪魔なのだろうかとも思い、ありがたく貰うことにした。
「そうしてくれると助かる」
宝珠を己の首にかけるマリアを見、ソウルイーターはそう呟いた。
「汝、これからどこへ行くつもりかや?
貰ったばかりの宝珠を手元で弄びながらマリアが問う。
「東の司法国家・セリカスタンだ」
ソウルイーターの答えに、マリアは目を丸くした。
「妾と同じではないか」
「そうなのか?」
「同じならば、共に行かぬか? その方が色々と楽しめそうだ」
旅は道連れとも言うしの、と笑うマリアに、ソウルイーターは少し躊躇ってから頷いた。マリアは大仰に頷き、彼を先導するように先に立って歩き出した。
「何処へ行くつもりだ?」
「関所だ。ここからそう遠くはないからの」
ソウルイーターは首を傾げる。北方の関所はこんな森のそばにあっただろうか?
「ここはかつて戦乱の時代に使われたもの。今は寂れて使う者はほとんどおらぬが、妾は事情があって今はここしか使えぬ」
「手形でもなくしたのか?」
「無礼な。家に忘れただけじゃ」
なくしたよりも性質が悪い、というのはこの際言わないでおいたほうが得策だろう。
「そういえば汝、盲との噂だが事実かや?」
扉の前で錠を弄りながらマリアが問うと、ソウルイーターは少しだけ眉を上げた。
「確かに俺はあまり眼が見えない。だが完全に盲目というわけではないな」
「そうかや。ならば能力のことは? 魂を喰らうというのは真か?」
「魂はわからんが、生物であればエナジーを吸い取ることはできる。多量に吸い取れば死なすこともあるから、まぁ事実だろうな」
「ふむ、難儀な能力よの」
マリアは錠を弄ったまま応える。その様子にソウルイーターは訝しげに首をかしげた。
「……さっきから何をしているんだ」
「関所の錠がどうしても開かなくてな。やはり髪留めでは難しいか」
「鍵はないのか?」
「あったらとうにそれで開けておる」
不機嫌そうなマリアにソウルイーターはしばし考え込む。
「…お前の魔術で開けられないのか?」
ソウルイーターの提案にマリアが目を丸くする。
「その手があったか。しかしわらわの力では錠を吹き飛ばすことは難しいだろうな。魔力が足らぬ」
「増幅装置とやらを使えばいいだろう」
「……何故それを早く言わん」
自分で気づけ、と言いたいのをこらえ、ソウルイーターはその場から一歩退く。それを見届けてからマリアは扇を開き、思い切り横に凪いだ。胸元の宝珠が強く光を放ち、先ほど機械獣たちを攻撃したものとは比べ物にならないほどの暴風が関所を見事に破壊した。
「む、やりすぎたか。初めて使う故、調整が効かぬの」
宝珠を手のひらで転がしながらマリアが呟く。
その正面には大小の砕かれた石が、まるで爆弾でも落としたかのように至る所に散乱していた。
ソウルイーターは風の余韻に髪を乱しながら、道連れの相手を間違えただろうかと溜息をついた。
文章部屋へ