真っ白なその部屋は一二畳ほどの広さがあった。入り口の正面に設置された大きな窓から純白のレースカーテンを通して柔らかい光が差し込み、白く柔らかな絨毯を敷き詰めた床の至る所に転がっている、色とりどりの子供用の玩具を優しく包む。
部屋の中央に据えられた木製の大きな揺り椅子に腰掛けた少年は柔らかな光に抱かれたまま大きな欠伸を漏らし、ヤハウェは自分の人形の名を呟く。けれど、その呼び掛けに答えるべき子供はもういない。純白に染め上げられた広い室内にいるのは彼一人だ。一瞬悲しげな表情を見せたヤハウェは、しかしそれを隠すように大仰な溜息を吐いた。
「……あれは玩具だったんだから。玩具はいずれ壊れる物。そろそろ飽きてきてたところだし、丁度よかった」
自分に言い聞かせるように言葉を吐き出すヤハウェ。だが口調に僅かに普段と異なるものが混じる。
ヤハウェは苛だらしげに椅子に添えてあった白い柔らかなクッションを窓に向かって叩きつける。強い力で投げられたクッションは透明な窓ガラスにぶつかり、白いカーペットの床に音もなく落下した。
「………たかが玩具相手に俺が寂しいなんて思うわけないじゃん。バッカらしい」
静かに目を閉じてみたが、どうしても眠れない。眠ることを諦めたヤハウェは椅子から下り、緩慢な足取りで部屋を後にした。
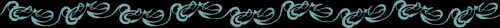
「ソノキっ!」
呼びかけられて後ろを振り返れば、白い髪を腰まで伸ばした子供が駆け寄ってくる。
「何?」
「あれ」
園樹の腰に抱きついたフィーが指差した先は、蒼い空。目を凝らせばぼんやりと見える昼間の小さな星を、楽しそうにフィーは見つめる。
「ヤハウェっ!」
「あぁ、そうだね」
園樹はセルペンスがいつもするように白い頭を優しく撫でながら応えた。フィーの大きな瞳が嬉しそうに細まる。
あれから、四ヵ月、フィーはこちらの世界で過ごしている。それはフィーが望んだ事で、園樹は特に追求はしなかった。
四ヶ月前、闇は園樹のイメージした剣の力で精神のみフィーの体から分離し、元々取っていたフィーを二十年ほど成長させたような美丈夫の姿に戻って何処かに行ってしまった。以来、闇がこちら側にコンタクトを取ってくる事はない。恐らく何処か他の惑星あたりでまた眠っているのだろう。
柔らかな南風が二人の頬を撫で、髪を僅かに乱して走り去っていった。フィーは僅かに眼を細め、けれど星から目を離さずに無邪気に微笑んでいる。
あの頃と比べ、フィー限定での話だが、園樹の子供嫌いも嘘のようになくなっていた。
「ヤハウェ……」
「あの人に会いたい?」
園樹が訊くと、フィーは星から目を離し、花の咲くような微笑みを園樹に向けた。
「………。ソノキといるっ!」
暫しの間考え込み、けれど普段通りに自分を見上げて笑うフィーの愛らしい仕草に、園樹はふと思う。
……今の間はいったい何だったのだろう。いや、さすがにあのヤハウェって人、いや正確には神だけど……あの人はフィーの親っぽいのかも知れないし、他にも色々懐いてたみたいだけどさ。ここにいるって決めたのは自分なんだからもうちょっと……ねぇ?
『フィー!』
「っ! ヤハウェ!」
不意に脳内に響いた声に反応し、フィーが元気に手を挙げる。同時にヤハウェの姿が瞼の裏に浮かび上がった。
『フィー、そんな汚物と一緒にいたら悪影響だから早く帰ってきな。一緒にお風呂入ろ』
「汚物って……失礼極まりないですね」
『なに? 事実を言われてキレるってことは自分でも自覚してるって事だよね? 可哀想だねぇ、生まれながらの汚物は。どれだけ頑張っても俺みたいに輝かしくはなれないものねぇ』
ヤハウェは柔らかく微笑みながら嫌みを連発する。だが今回は園樹も負けてはいなかった。
「フィーはこっちが良いって言ってるんですし、そんなにフィーがいなくて寂しいならこっちに来たらどうですか? ソファくらいなら貸しますよ」
『うるっさいなぁ。寂しくなんかないって言ってんじゃん。いい加減にしろよ』
「寂しいんですよね?」
『う、うっさい! 誰がそんなこと…』
「今泣きそうになってるでしょう? 声が震えてますよ」
『うっさいっつってんだろこの馬鹿! 洪水で死んじまえっ!』
「出来ないこと言っちゃ駄目ですよ。このあいだ剣を創ったときにそういう力、使い果たしちゃったじゃないですか」
『……っ! この揚げ足取り!』
「なんとでも。とりあえず、フィーは今の所こっちに居たいそうですから、もう暫く預かっておきますね」
『フィーを取るな、この馬鹿!』
「馬鹿って先に言った方が馬鹿だって言葉、知ってますか?」
『しらねぇよ、そんなん。俺は神だから偉いんだ!』
「無能な神って哀しいですね」
『喧嘩売ってんだよね?』
「もちろん」
『よっし、特別に許すから今すぐこっちに上がってこいよ、人間。こないだは闇のせいで有耶無耶にされちゃったし、出血大サービスでカミサマの力、とくと見せてやるよ』
「暗に僕に死ねって言ってるんですね」
『あったりまえじゃん。そんなことも判らないなんて、やっぱり頭の中まで汚物まみれなんだね。ああ、存在が汚物だからしょうがないか』
「そんな心が真っ黒なのがカミサマの条件なら、僕は汚物でいいです」
端から見れば園樹が独り言を延々と喋っているという奇妙な光景にも一切感知しないまま、神と人間の下らない口論は徐々にエスカレートしていく。フィーは飽きてきたのか園樹から離れ、公園の中を飛んでいる蝶を拙い足取りで追いかけ始めた。
「いー加減にしなさい、ソノッキー、ヤッ君」
不意に園樹の背後から声が聞こえ、振り返る。そこには髪を風に軽く弄られながら立っているセルペンスの姿があった。冬の装いから一転、全体的に黒っぽい事に変わりはないが、長袖のハイネックは春物らしい薄手になっていた。
「セルさん…」
「ソノッキー、ダメだよ。ヤッ君はちょっとからかうとすぐムキになっちゃうんだから。まぁそれはそれで楽しいけど、あんまし遊び過ぎてフィーから目を離しちゃダメだよ?」
「え……あ、フィー!?」
慌てて園樹が公園内を見回すと、フィーは公園の中心に位置するジャングルジムの頂上で、近くを舞う蝶に手を伸ばしていた。重心が傾き、体がぐらりと揺れる。急いで駆け寄り抱き下ろすと、フィーは抱きしめられたまま少々不満そうな顔で園樹を見上げた。
「危ないからそういうことはしちゃ駄目だよ」
「う……?」
良く判って居ないように首を傾げてみせるフィーに苦笑し、園樹は優しく抱き下ろして解放した。降ろされても暫しの間首を傾げていたフィーは、それでも暫くすると何か納得したように大きく頷き、また蝶を追いかけ始めた。その様子を微笑ましげに見つめ、セルペンスは大きく伸びをした。
「それにしても、ようやく落ち着いたって感じだよな。闇が消えてからしばらくはヤッ君がフィー絡みでよくちょっかい出してきてたし」
「今でも僕はちょっかい出されてます」
「闇もあれから音沙汰ないし」
「スルーですか。そういえば……どこ行ったんですかね、彼。行き先も言ってなかったし」
「俺もやっと就職決まったし」
「いや、話振ったほうが投げてどうするんですか。というかホントにやっとですね。今までプー太郎だったんだから、フィーが来た分しっかり働いてください」
「プー太郎言うなって。てかなんで知ってるんだよ」
「前にセルさんが調べてみろって言ったから、調べてみました」
素っ気なく答える園樹に、知られたくなかったのになどと言いながらセルペンスは頭を抱える。
「で、どんな仕事になったんですか?」
「ん? よくぞ訊いてくれました! なんと渋谷駅周辺だ!」
「へぇ……」
胸を張って言うセルペンスに園樹は心中で嘆息する。園樹が問うたのは仕事の内容であって職場ではない。今時は渋谷駅周辺だって仕事など幾らでもあるが、条件が厳しいところが多く、園樹のクラスメイトの中ではかなり不評だ。
「以外に反応薄いな。しかも仕事内容は俺にぴったりだ!」
「聞くのが怖いからもう言わなくて良いです」
だんだん訊くのが面倒になって園樹はやんわりと断る。こんな彼がまともな職に就けるとはあまり思えない。むしろセルペンスなら小説やマンガなどの王道、裏の社会とやらに片足を突っ込んだとしてもなんら不思議ではない。むしろ喜んで入っていきそうな気がするのが不気味だ。
「自分から訊いてきたくせに引くな。いいから言わせろよ。なんかパソコンとか漫画がいっぱいあって、長くて一月単位の宿泊もできて、しかもドリンクバー付きだ」
「……ネカフェですか。とりあえず就職おめでとうございます。これからはしっかり働いてください」
「でもそれぞれの個室が狭くて、使う客によってはけっこう汚いから、掃除結構大変らしいんだよな。ヤダなぁ、肉体労働」
俺はもっとスマートな仕事がいいのにな、とぼやくセルペンスに園樹は呆れて溜息を吐く。
「別にいいじゃないですか、人間と違って体力有り余ってるんだからそれくらいはしてください」
「何言ってんだソノッキー。俺がいくら神に近いエデンの蛇でも肉体的には人間の成人男性と何ら代わりはないぞ」
「えばらないで下さい」
セルペンスのおちゃらけた仕草に嘆息しつつフィーに目を戻すと、フィーも丁度こちらを向いたらしく目が合って、花が開くような笑顔と共に大きく手を振られた。軽く手を振り返しつつ、園樹は青い空を見上げる。空には未だ昼間の星がぼんやりと輝いていた。
『何見てるのさ、人間? こっちに来たくなったとか?』
ヤハウェがニヤリと口角を吊り上げ、からかうような口調で再び声をかけてくる。まるでテレビ電話みたいだと園樹は苦笑し、ブランコで遊んでいるフィーを呼び戻した。
「フィー、そろそろ帰ろう。もうすぐ四時になるから、また少し寒くなるよ」
フィーは大きく頷き、ブランコから降りて園樹に向かって走ってくる。そして服の裾を軽く掴み、抱いてほしいと腕を伸ばした。
そんな日常に園樹は微笑み、いつものように彼を抱き上げ、隣に置いてあった鞄を掴み、まだ何か喋りたそうにしているセルペンスに呼びかけた。
「セルさん、そんなところに突っ立ってると邪魔ですから早く来てください。じゃないと、フィーをうちの子にしますよ。母さんたちもフィーのこと気に入ってるみたいだし」
「駄目に決まってんだろ、バァカ」
軽口を叩きつつ苦笑し、セルペンスは隣人の背を追った。
ほんの些細なことから始まり激変した、園樹の、フィーの、セルペンスの、ヤハウェの非日常。
そして四ヶ月後に新たな形で戻ってきた、彼らの日常。
それがこれからも続いていくかは、彼らしだいだろう。
―――The End